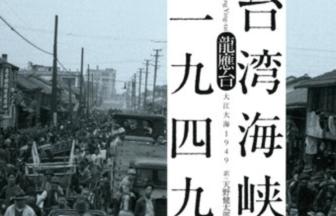【 金庸 / 武侠小説 / 書剣恩仇録 / 台湾人 】
目次
台湾の男子なら誰もが読んでいる金庸の武侠小説?!
以前にこんなことを聞いたことがある。台湾人の男子ならみんな金庸を読んだことがあると。
本当かどうかは知らない。けれども例えば今40歳代の日本人であれば、若い頃に司馬遼太郎の歴史小説を読んだことがあるだろう。『竜馬がゆく』が特に人気の高い作品で、1990年代の財界人であれば『坂の上の雲』を愛読書に挙げる人も多かった。もう一世代前だと、山岡荘八の『徳川家康』(全26巻)だろうか。サラリーマンのバイブルとも称された作品である。
歴史小説好きなら、さらに台湾出身の陳舜臣の作品から中国史に入っていく人もいるかもしれないし、司馬遼太郎の『項羽と劉邦』、吉川英治の『三国志』、あるいは浅田次郎の『蒼穹の昴』、宮城谷昌光の膨大な作品群へと読書を広げていった人もいるだろう。
いずれにしても「歴史小説」というジャンルは、ひょっとすると日本ならではのものなのかもしれない。基本的な史実には基づいているが、人物像は作家の解釈と想像で比較的自由に描かれる。
これと比べると、欧米では小説ではなく、史実に基づいた歴史書が好まれている。特にローマに関しては、書籍だけでなく、多くのドキュメンタリーやドラマが繰り返し放送されている。もちろん、塩野七生の『ローマ人の物語』も、日本では人気が高いが、これもやはり歴史小説というジャンルに入るだろう。
小説である以上、著者の人間観と想像力が作品に大きく反映されており、史実から離れた解釈も少なくない。司馬遼太郎は特定の人物に焦点を当てて、ヒロイズムを掻き立てるストーリーが多い。これに対して、山岡荘八の徳川家康は、ときに退屈するほどの人と組織のあり方を長々と描いているが、30歳手前で読んだ私は大きな感動を得られたし、今も自身の処世において役立っている。それは個人のヒロイズムを超えて、社会の仕組みや制度への目配りがあるからではないかと思う。宮城谷昌光の作品は、中国の古代史が中心だが、やはり描いているのは国家運営戦略であるように思う。
国民的人気のある歴史小説は、日本人の精神のあり方を形作っているところがある。
であれば、台湾など中華世界で圧倒的な人気を誇るという「武侠小説」というジャンル、中でも絶対的な存在感のある金庸の作品からは、台湾人の精神のあり方を多少なりとも形作っているところがあるのではないか。
武侠小説の第一人者、 金庸の処女作 書剣恩仇録
金庸(Jīn Yōng)は武侠小説の代表的な作家で、香港の小説家である。2018年に94歳で亡くなった。
1995年に発表した第1作が『書剣恩仇録 秘密結社 紅花会』《全4巻》である。日本語訳はすでに絶版となっており、古本でしか入手できない。

金庸は1巻の冒頭「日本の読者諸氏へ」において、吉川英治や井上靖、司馬遼太郎の小説がとても気に入ってると語っている。その上で、以下のようにとても興味深い指摘をしている。
中国の侠士の基本的な考え方は、日本の武士道とも違いがある。武士道の中心は「忠」の思想である。恩ある主君に忠を尽くし、命を犠牲にしても惜しくはないという考えだ。中国の任侠道の中心は「義」である。孟子のいう「生を捨てて義を取る」であり、義が命より大切なのである。
さらに「義」に関しては、
「義」という文字には、通常二つの意味がある。一に正義。筋の通ったこと、正しい道理である。二に義気。他者の利益(友人、妻子、兄弟、仲間、果ては行きずりの人間も含む)を重んじ、人の為におのれを捨てることである。
忠と義。なるほどなあ、といろいろと考えさせられる。
本書を読み始めると、清朝の打倒を目指す紅花会という幇会(秘密結社のような組織)の腕に覚えのある人物達が次々と現れる。そのメンバー同士を結びつけているのが、まさに「義」である。仲間のためには平然とおのれの命を捨てるのである。
さて、本書の内容は直接読んで頂くとして、私が個人的に感じた特徴を幾つか挙げてみたい。
1.存在感のある強い女性の活躍
おそらく武侠小説と日本の歴史小説との一番大きな違いは、ここではないか。
気性が強く、少々わがままな跳ねっ返り娘が、とにかくたくさん登場するのだ。
しかもそうした女性にこそ魅力を感じる男性陣が多いことも、驚くばかりだ。
日本の歴史小説では、女性が登場しても奥方として武将を蔭で支えたり、あるいは時に忍者などの工作者として活躍したり、場合によっては将軍家を後ろから差配するといった権力志向の女性も登場するが、中国の武侠小説のように、跳ねっ返り娘が次々と登場して、しかもストーリーの中心的存在を担っているという例は少ない。
実際、台湾でも中国でも女性は強い、と聞く。わがままであることはネガティブなことではなく、むしろ直情型の、口は悪いけれど情に厚い女性は、男性にとって憧れになっている感さえある。
2.武術の技への尊敬の念
日本の歴史小説で、武術の技と心といえば、やはり吉川英治の『宮本武蔵』で、私の中学生のときのバイブルだった(笑)
しかしたとえば『竜馬が行く』になると、各人ともに若き日は剣道でならして、道場を代表するような剣術を身に付けるが、あくまで心技を鍛えるためのものであって、政治的に活動をし始めると、もはやこれらの武術を使うことは稀だ。武術で培った精神と呼吸で、大事な交渉などの局面を乗り切っていくのである。
これと比べると、中国の武侠小説は、ちゃんばらではなくて、一人一人がその武術の道の第一人者であり、師父から免許皆伝を得た筆頭格であり、常に現実離れした格闘が繰り広げられる。体格差はほとんど無視されており、格闘技術だけで勝利するところがカンフー映画を想起させる。これは娯楽作品としても楽しまれているところの大きな特徴なのだろう。
3.義理と人情
スケールの大きなストーリーなのだが、悪き権力者に立ち向かう正義漢たちという構図が明確で、金庸のいうとおり、まさに「義気」の世界観となっている。男気といいたいところだが、女性陣も同様の行動力があるので「義気」の方がよい。
こうなってくると、比較すべくは歴史小説というよりも、池波正太郎や藤沢周平といった作家の「時代小説」なのかもしれない。時代小説は登場人物が市井の人々、一般庶民、下級武士などが中心だが、武侠小説では歴史を大きくデフォルメしつつ、義理と人情に溢れた娯楽小説となっている。
というわけで、金庸の武侠小説から、台湾人の気風が浮かび上がるかと期待したものの、これだけを読んで、そのような一般化をしていくのは、ちょっとムリがあるという結論となった。
もちろん若き日に夢中で読んだ本に描かれた人の生き様は、それがその人にとっての理想として強く刻印されれば、生涯にわたって一定の影響を及ぼすだろう。とはいえ、時代が時代である。本を読む若者も少なくなっており、テレビでは全世界の映画やドラマが幾らでも観られる時代には、もはや「その人それぞれ」というほかない。
人は多面的なもので、仕事柄、分析的で計画的と思われている私も、いざ自分のこととなると、思いついたら考えるよりも行動、という抗えない気質を持っている。危なっかしいことこの上ない。
台湾人の人間関係 〜 関係(グワンシ)とメンツ
『関係(グワンシ) 中国人との関係のつくりかた』という本がある。
関係(Guanxi)システム研究の第一人者で、香港大学商学院国際マーケティング学部長であるDr. David K. Tseが著したこの本は、香港や中国でビジネスを手掛けるビジネスパーソンを対象にして書かれた、グローバルコミュニケーションの教科書である。
中華世界の人間関係の種類、そして内輪に入っていくための贈り物の交換、、、日本人的感覚からすると、契りを結ぶ、あるいは関係を切り結ぶ、といった方が適切な感じさえするほど、重みのある濃厚な人間関係こそが、行動の基盤となっているようだ。
これもまた、上下関係の「忠」よりも、横のネットワークを重視する「義」の世界観といえるのではないか。
日本人からすると理解しがたいこと、あるいは不思議に感じていたことが、ふっと霧が晴れるかのように、中華系の人たちの行動特性の元になっている考え方が解説されている。分かったからといって、それが本当に理解して実践できるかというと、これはまた別の問題なのだが(笑)
『異文化理解力――相手と自分の真意がわかる ビジネスパーソン必須の教養』
金庸は15作品を残しているが、ある方は以下が良かったと紹介してくれました。
ご興味のある方はいちど 金庸の武侠小説の世界に浸ってみてください!

【 台湾 と 日本 / 台湾人 / 台湾 社会 】 一つの国を理解するということ 他国を理解するという営みは、とても難しい。数千万人が住む国を理解するということは、人間と組織と社会を理解することだ。たまたま知っている数人の友人をイメージして、あるいはネット上の意見を鵜呑みにして、この国は親日国で...

【 台湾 映画 / セデック バレ / 霧社事件 】 台湾の国民的映画『セデック・バレ』 台湾の映画「セデック・バレ」を御存じだろうか。「セデック・バレ」の第1部「セデック・バレ 太陽旗」(2011年)は、台湾での台湾映画歴代興行収入において「海角七号 君想う、国境の南」(2008年)に次ぐ第2...